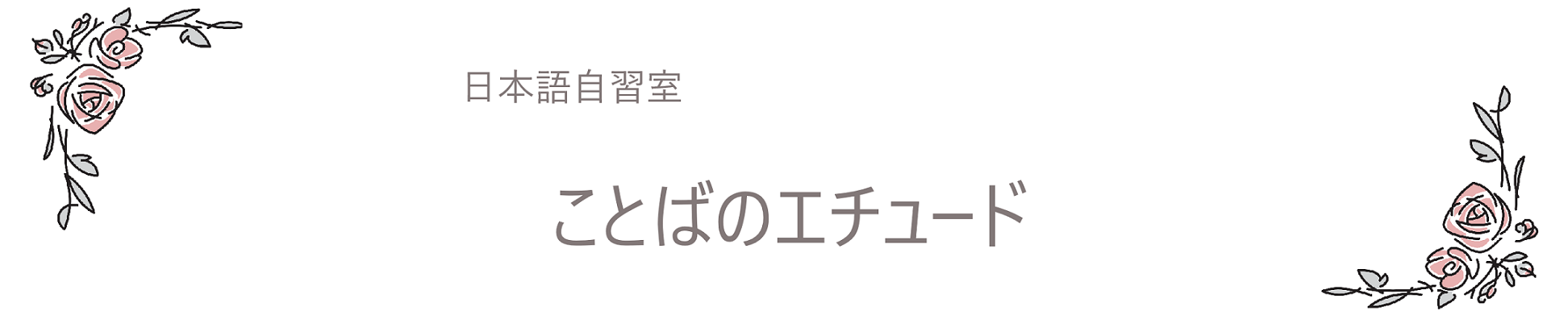常用漢字の役割はどんなもの?
漢字の種類は本当にたくさんあって、その数は5万とも10万ともいわれます。これを好き勝手に使用すれば習得に時間がかかりすぎるだけでなく、習得の度合いに個人差が生じるため公用語としての役割が果たしにくくなり、対応しなければいけないIT技術の面でも不利です。そのあたりは国のほうでもきちんと考えていて、「現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安」として2,136字を選んで「常用漢字」とし、基本的にこの漢字を使ってくださいと示しています。そして、義務教育を終えるまで、つまり、中学卒業までにすべての常用漢字を学習します。そして、ほぼその漢字の範囲内でさまざまな情報が得られるようになっているんですね。
公用文のうちの広報や、新聞、雑誌、放送など、一般市民に広く情報を提供する責務を負う立場であれば、常用漢字以外は使用せずにひらがなにするか、ほかの表現に言い換えるか、使用する場合には、初出のものにふりがな(ルビ)を付すことになっています。

交ぜ書きの「まい進」とか「被ばく」とか「えん罪」とか、ちょっと脱力するけど、みんなに読んでもらうためなんだね。
誰に向けての発信なのかで表記が異なる
ここで大事なのは、常用漢字表にないものは用いてはいけないのかという疑問です。答えはノーで、文化審議会の方針でも、例えば公用文においては、「専門的な知識がある人」「ある程度の専門知識がある人」「専門的な知識を特に持たない人」にざっくりと分類して、解釈の違いを生まないように専門用語の表記をそのまま用いるものと、常用漢字内でとどめ読みやすさに配慮するものと、その中くらいのものとに区分しています。
議事録・公開資料等 ある程度の専門的な知識がある人を想定
解説・広報等 専門的な知識を特に持たない人を想定
ですから、例えば「まい進」という場合、専門的な知識を有する人が読むことが前提であれば、わざわざ「まい進」と交ぜ書きにせずに、漢字で「邁進」としていいのです。そこは誤解のないようにお願いしたいと思います。実際、議事録表記では「邁進」「冤罪」「被曝」などとしていて、交ぜ書きは採用していません。議事録の目的は正確に伝えることなので、むやみに漢字にするということではなくて、誤解を生む表記を用いないということからそのようにしています。
もちろん、大学の講義でしたら「信ぴょう性」は「信憑性」、「急きょ」は「急遽」、「らく印」は「烙印」と表記するでしょうし、医学書でしたら、「すい臓」ではなく「膵臓」、「産じょく期」ではなく「産褥期」、「白せん菌」は「白癬菌」と書いてあると思います。どういった対象を読み手として想定しているかによって表記はおのずと異なってくるんですね。
書くのではなく、文字を打つ時代の留意点
だからといって、もちろん好き勝手に使っていいということではありません。文字は書かずに打つ時代となった現在、文字コードを意識しなければならないためです。文字コードとは文字をコンピュータで処理するために文字に番号を割り振って定義したもので、標準的な文字コード以外の漢字を使用すると、環境によっては文字化けするなどの悪い影響を及ぼしてしまいます。常用漢字内であればその心配は皆無ですから、やはり常用漢字表は頭に入れておいたほうがよいことになりますね。

なるほど。「宮崎駿(※崎=たつさき)監督」とか、「草なぎ剛(※なぎ=弓へんに「剪」)さん」とか、注釈入りの表記を見かけるのはそのためなんだね。
常用漢字表には読み方も示してある
常用漢字表は漢字の種類だけを示してあるのではなく、読み方も記載していて、基本的に読み方の欄にない読み方は用いません。例えば、「想」という漢字の読み方の欄を見てみると、「ソウ」「ソ」という読みしか載っていません。ですから、「感想(かんそう)」や「愛想(あいそ)」とは書けますが、「想う(おもう)」とは読ませないわけですね。原則として「おもう」は「思う」を使ってくださいということです。このように、常用漢字表には漢字の種類だけではなく読み方についても指定があるという点は覚えておいたほうがよいと思います。
_ | ソ | 愛想
漢字を選ぶばかりではなく、漢字にするかひらがなにするかも常用漢字表に従います。例えば、「私財をなげうって学校を建てた」という場合の「なげうつ」は、「投げ打つ」ではなくて「擲つ」です。ただ、「擲」は常用漢字外なのでひらがなで「なげうつ」と書くといった具合です。

「想う」とか「逢う」とか「淋しい」とか、歌の歌詞にはよくあるけど、一般的には使わないほうがよさそうね。
常用漢字表には付表がある
常用漢字表には最後に付表があります。これは特別な読み方をするものを示していて、116種類が掲載されています。この中には義務教育修了までに学習しない読み方もあります。
例えば、常用漢字表で示された「退」の読みは「タイ/しりぞ(く)/しりぞ(ける)」の記載しかありませんが、付表を見ると「立ち退く(たちのく)」とあって、「立ち退く」に限って「退」を「の」と読んでよいということを示しています。

こりゃあ、常用漢字を覚えるのが大変なんじゃなくて、常用漢字かどうかを判別するほうが大変かも。
言葉は用いる人々が育てていくもの
最近では個人での情報発信が非常に増えて、これまでの伝統的な情報源を凌駕(りょうが)するほどです。また、文字はもはや「書く」ものではなく「打つ」ものになったことで、自分では書けなくても気軽に漢字変換ができるようになりました。だからこそ、当て字や難読漢字を乱用するのではなく、伝わる日本語、わかりやすい日本語を用いる配慮が必要だと思います。
ただ、常用漢字は固定的なものではなく、これから新たに採用されたり、逆に常用漢字から外れるものが出てくる可能性があります。ちなみに、現在使われているのは2010年(平成22年)に改訂されたものです。言葉の使い方は国が決めるのではなく、国民が用い育てていくものですが、ただ、バラバラでは困るので基準を示しているということですね。
難読漢字は用いないほうが知性的
当て字の乱用はかえって知性を疑われますし、表外字のオンパレードは独りよがりな文章になりかねません。「蟷螂」をカマキリ、「伯剌西爾」をブラジルと読めたからといって、それが教養の証しということではないと思いますし、実生活でもそんなに意味はないと思います。もちろん、エンターテインメントとして楽しみながら雑学が増えることはよいことだと思いますけれどもね。
少し前に、西村博之氏がSNSで、国語教育においての古文・漢文は必修ではなく選択制にしたほうがよいと発信されていました。賛否はいろいろあるにしても、今の時代、限りある学習時間を古文・漢文に割くよりも、情報教育や理数教育など、ほかにやることがたくさんあるという意図だと思います。
実は、似たような考え方は江戸末期からあったようです。「日本近代郵便の父」と呼ばれ、1円切手の肖像にもなっている前島密は、国民の間に学問を広めるために漢字の使用をやめて全部ひがらなにすべきだと主張したそうです。お気持ちは手に取るようにわかりますが、漢字をなくしていたらとても不便になっていたでしょうから、なくならなくてよかったなと個人的には思います。
すべてひらがなにすべきだという主張はほかにも多くありましたし、漢字、ひらがな、カタカナが混在する日本語の将来を危惧した先人たちが、アルファベットに置き換えたローマ字を浸透させようとした試みもありましたよね。韓国語が漢字を捨てたのはそれなりの大きな理由があったためですから、どれが正解ということではないのだと思います。
さまざまな議論はおいておくとしても、移住者の増加やAIの台頭がこれから日本語をどう変えていくのか、私も楽しみに見守っていきたいと思います。

日本語は魅力的だけど、複雑なために不利な面もあるのね。