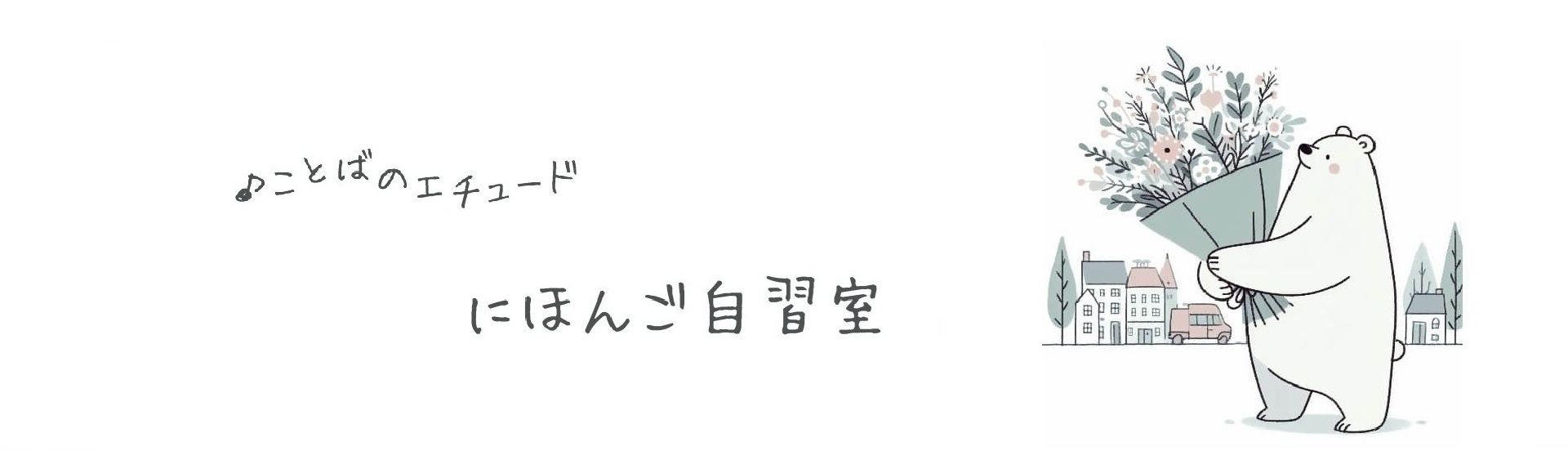プロフィールページにアクセスしていただきありがとうございます。ルームチョ@にほんご自習室です。どうぞよろしくお願いいたします。簡単に私の経歴をご紹介したいと思います。
教職を経て起業
大学卒業後の数年間は教員をしていました。最初に高等学校を経験し、中学校と小学校の経験もあります。それぞれ1校ずつ、合計で5年ほどです。ただ、校種を変更して適性を探ってみましたが、結果として、私自身は教える仕事よりも一人で業務に集中する働き方のほうが向いていると考え、その後、大きな決断でしたが起業しました。現在は一人法人の代表をしています。
業務の内容ですが、音声のテキストデータ化や文章のリライト、要約文の作成を柱とし、自費出版の編集やコラムの執筆の経験もあります。軌道に乗るまでに少し時間がかかりましたが、やがてスキルを認めていただき、ありがたいことに全国各地からお仕事を頂戴できるようになりました。
表記が異なることへの気づき
取引先は、大学や研究機関、官公庁、法律事務所や出版社、放送局など多岐にわたりましたので、おのずと表記の違いを学んでいきました。官公庁であれば公用文の表記がありますし、特に私は議事録作成に多く関わりましたので、その場合には議事録用の表記を用います。これは国会議事録で用いられている表記になります。
出版社からの依頼であれば、基本的に新聞表記ですし、公共放送局からの依頼も非常にたくさん承りましたので、そうするとまた独自の表記になります。現在はAIに移行した業務もありますが、こうやって、毎日、日本語の表記と格闘しましたので、得られた知見も増えていきました。
個人発信の時代を支えたい
21世紀に入ってからというもの、個人発信の情報が非常に増えています。特にコロナ禍以降は、SNSやブログだけでなく、noteなどのコンテンツ配信も広がりをみせ、個人の発信が既存のメディアを凌駕する勢いですが、もちろんそれは歓迎すべきことだと思います。
でも、弱点もあります。大手メディアであれば、社内で定めた表記をたたき込まれ、複数のチェックを経て初めて発信されるのに対し、個人発信は誰のチェックも経ることがないため、訂正される機会に恵まれないという点です。
日本語の表記は複雑ですので、いちいち正確に覚えていられないというのも事実です。また、国語辞典には意味は書いてあっても、詳しい表記については触れられていません。それなら、表記に特化した、いわゆる「表記辞書」のようなサイトがあれば便利なのではないかと考え、このブログを立ち上げました。
ことばは無尽蔵ですので、もちろん網羅できていませんが、かなり充実してきましたし、これからも更新を続けていきますので、ぜひ「お気に入り」に登録して、ブログの検索窓から調べたい語を探すなどして活用してみてくださいね。
このブログの主たる参考文献
○国語辞典
『広辞苑(第七版)』岩波書店
『大辞林(第四版)』三省堂
『明鏡国語辞典(第三版)』大修館書店
『岩波国語辞典(第八版)』岩波書店
『三省堂国語辞典(第八版)』三省堂
『新明解国語辞典(第八版)』三省堂
『現代国語例解辞典(第五版)』小学館
○漢和辞典
『漢字源(改訂第六版)』学研
『漢辞海(第四版)』三省堂
『新字源(改訂新版)』角川書店
○表記辞書
『最新公用文用字用例集(増補版)』(ぎょうせい公用文研究会編)
『新聞用字用語集(記者ハンドブック)』(共同通信社)
『NHK漢字表記辞典』(NHK放送文化研究所編)
『新訂 標準用字用例辞典』(公益社団法人日本速記協会)
○語源辞典
『新明解語源辞典』三省堂
『日本語源大辞典』小学館
『暮らしのことば 新語源辞典』講談社
その他、必要に応じて多数。