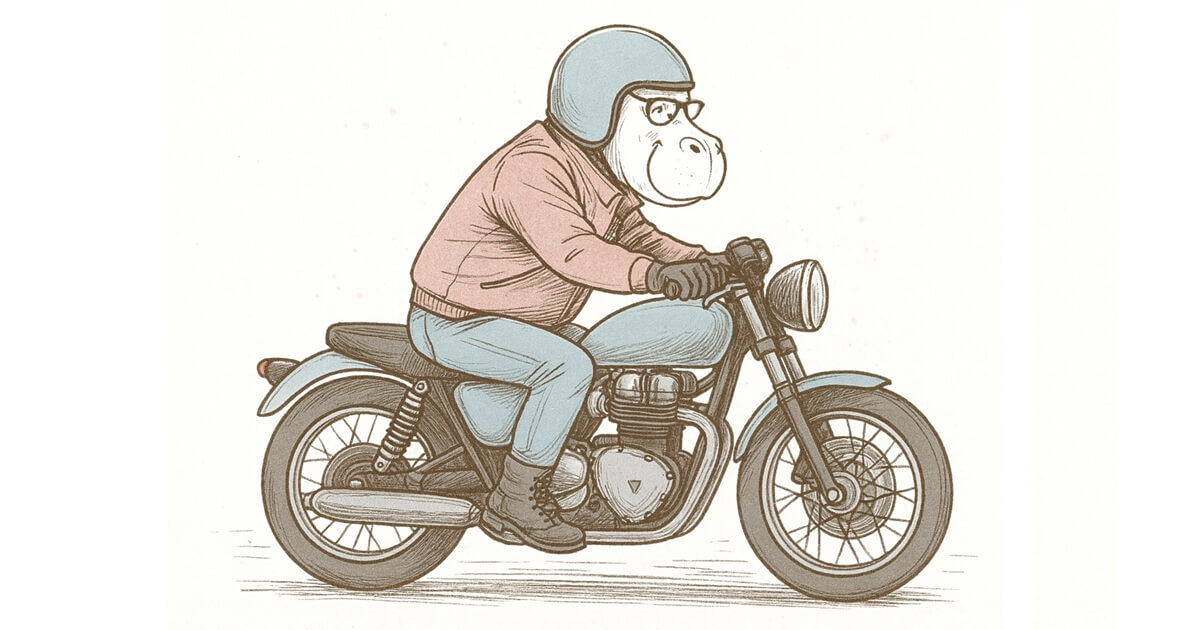「業」と「技」の違いを確認しましょう
「わざ」というときに、「業」と「技」のどちらにするか一瞬迷ったことはありませんか? なんとなく使い分けていますが、ここで念のため確認しておくことにしましょう。
業:意識的に行われた行為や出来栄え
技:手足を使った技術や技能
ざっくり捉えれば上記のような意味になります。具体的に用例で確認していったほうが早いですね。
【業(わざ)の意味と使い方】
早業:素早くて巧みな動作や行い
・3分でできる早業レシピをご紹介します。
離れ業:人を驚かすような芸当
・サーカス団の離れ業には驚かされた。
至難の業:とても難しい行い
・これを3日でやるのは至難の業だ。
神業:神でなければできないような行い
・神業かと思うようなジャンプに目を見張った。
人間業:人間の行い
・とても人間業とは思えない出来栄えです
業師:技能(または戦略や駆け引き)にたけた人
・彼はまさに政界の業師だな。
【技(わざ)の意味と使い方】
技を磨く
・ますます技に磨きがかかっているね。
技を覚える
・新しい技を覚えたことで自信がついた。
技を競う
・集まった高校生がロボット製作の技を競った。
寝技
・柔道の寝技が決まった。
すご技
・達人のすご技を間近で見た。
「離れ業」は「離れ技」とは書かない理由
こうしてみると、「技」は手足を使ったトレーニングで身につける技術・スキルのことで、「業」は、その技術の結果として成し遂げられた行為や出来栄えのことだとわかります。
では、サッカーなどで、例えばバイシクルキックが決まったときは、技術のことですから「離れ技」としたくなりますよね。でも、国語辞典には「離れ技」という語は載っていないんです。
ですから「離れ業」や「神業」は決まった成句として覚えてしまいましょう。シーン別に使い分けるのではなく、決まった形で用いるということですね。
(用例)
・彼はバイシクルキックという技を使って離れ業をやってのけた。
・彼女のブレイキンの数々の技は、まさに神業というべきだろう。

行為か技能かで使い分けるのね。
「業」を「ゴウ」と読むと悪い意味になるの?
「業」を単独で用いると「ゴウ」という読みにもなります。「業(ゴウ)」というのは仏教用語で、「前世の行為によって受ける現世おいての応報」のことで、「理性ではどうにもならないその人の性質や境遇」のようなことを指します。どうしてどうにもならないのかというと、前世の因果によるものなので、現世においてはお手上げなんですね。
「業が深い」というのは、前世の因果のせいで「不運が続く」場合に用いますが、「欲が深い」ことにも使われます。前世でよほどのことがあったので、現世において執着心や欲望などが顕著にあらわれてしまうのかもしれません。
また、「自業自得」と言ったりしますが、これも「自分の行いのむくいを自分自身が受けること」の意味です。善いこともしているはずですが、悪いことが起こった場合に用いられるので、「業」にはどうしても暗いイメージがつきまとってしまいますね。

「自業自得」といわれちゃうと何も言い返せなくなくなるよね。
「業」には「なりわい」という意味もあります
「業」という漢字そのものに「なりわい」という意味もあります。「なりわい」とは生活していくための仕事のことで、「なりわい」とひらがなで表記します。「生業」という字を当てることもありますが、その場合は「生業(なりわい)」とルビやふりがなで読みを示してくださいね。普通に読めば「生業」は「せいぎょう」になりますが、意味は「なりわい」と同じです。
・40年間、パンの製造をなりわいとしてきました。
・好きなことをなりわいにできたら最高なんですが。
・「なりわいづくり」によって移住者を増やしていきたい。
「巧み」と「匠」との違いについて
「技」というと「巧みな技」というように、「巧み」という言葉で修飾されることが多いですよね。「巧み」というのは形容動詞で、手際よく物事をしとげること、または物事にすぐれた技巧を凝らすさまのことを言います。
・巧みな話術で会場を魅了した。
・この工芸品には巧みな技が使われているね。
一方で「匠(たくみ)」というのは工作物を製作する職人さんのことです。ただし、常用漢字表には「匠」は「ショウ」という読みしかありませんので「たくみ」とひらがなにします。あるいは、どうしても「匠」を「たくみ」と読ませたい場合には、ルビやふりがなを添えると親切です。
「匠」は、熟語だとそれぞれの分野のプロフェッショナルのようなことですが、「匠」そのものに「すぐれた技能」という意味があるので、リフォーム関連のテレビ番組のように、「匠」を「技術の高い職人さん」の意味で用いることもあるようです。
師匠 巨匠 名匠 画匠 宗匠 工匠 石匠 など

劇的なものでなくていいから、リフォームしたいなあ。
「意匠」ってどんな意味?
「意匠」という言葉を耳にしたことがあると思いますが、これは「(造形物に)工夫をめぐらすこと」という意味です。「意」は「考えやアイデア」、「匠」は「すぐれた技巧」ですから、「意匠が凝らされた建造物だね」であれば、「デザインが工夫された建造物だね」ということになります。
○意匠登録って何を登録するの?
アイデアというのは持ち主を特定するのが大変です。特にデザインは、思いつくまでは大変ですが、似たものを製作することは容易です。それで、特許庁に「意匠登録」してデザイン自体を保護するわけですね。
おわりに
今回は「わざ」の使い分けを中心に、関連する言葉についてまとめてみました。
・「技」は、手足を使ったトレーニングで身につける技術・スキルのこと。
・「業」は、その技術の結果として成し遂げられた行為や出来栄えのこと。
・「神業」「離れ業」は、シーンを問わず決まった成句として使う。
言葉の背景を知ると、スポーツ観戦や伝統工芸の見え方も少し変わってくるかもしれません。皆さんも「これは技かな? 業かな?」と、日常の中で探してみてくださいね。
最後まで読んでくださって、ありがとうございました!